2025年 大阪・関西万博あましん × 共創チャレンジ
AMASHIN × Co-creation Challenge
オオムラサキから自然を考察
身近な自然とまちを考える会
会長 牛尾巧 氏
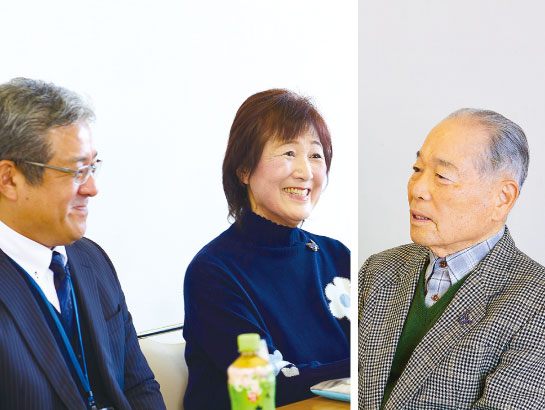
豊かな里山を背景に阪神間のベッドタウンとして発展してきた川西市。恵まれた自然環境を活かす形で1998年、身近な自然とまちを考える会(牛尾巧会長)が発足し、猪名川水系の水棲生物の調査が開始された。事の発端は環境省に登録を受けた環境カウンセラーで、会の副会長を務める石津容子氏が娘の理科の自由研究をサポートしたことだ。会は2014年に森林文化の醸成を図る兵庫県立丹波の森公苑を訪問。兵庫丹波オオムラサキの会の足立隆昭会長の指導を得て、環境省のレッドリストにも入っているオオムラサキの飼育・観察を始めた。同様の活動は東日本では盛んだったものの、西日本では先駆的な事例だった。
オオムラサキは、幼虫時代はエノキの葉しか食べず、成虫になってもクヌギなどの樹液しか吸わない。それが幸いなことに「日本一の里山」とも称される川西の里山には猪名川上流の初谷川流域をはじめとして、国蝶の生育に必要な植生が残されていたのだ。約10年におよびオオムラサキと向き合うなかで、活動には地元の子どもらが積極的に参加するようにもなった。川西市立明峰小学校の運動場の一画にケージを設置し、幼虫がさなぎになり、羽化を迎えるまでを身近に感じられるようにしたのだ。「さなぎを見せてまずは触ってごらんと声をかけると『かわいい』『生きてる!』という反応が返ってきて。何よりうれしい瞬間ですね」と石津氏。大らかな視線はオオムラサキの保護のみならず、川西の自然の豊かさを伝え、次代につなげていくことにまで注がれている。

1
オオムラサキから 環境保護の視点を
オオムラサキを教材として、川西が環境に優れた街であるとの認識を醸成。将来世代に向けたアピールを通して、川西といえばオオムラサキというイメージの定着を目指します。 現在は明峰小学校にのみ設置されているケージも、いずれは市内の小学校の多くをカバーしたいです。
2
環境都市・ 川西の魅力を掘り下げる
オオムラサキが生きられるということは、豊かな自然が保全されている証拠。美しいチョウからその事実に目を向けてもらい、間伐や炭焼きといった形で里山に人の手が入ることが、環境維持にいかに大切かということを学んでもらいます。その気づきを持続可能な里山づくりに活かします。



